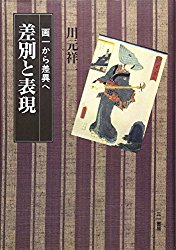
はじめに
1、諸学問の糾合と新しい視点
日本の社会で、長い間タブーの領域にあり、現代も未解決の問題とされる部落問題を、そうした歴史と現状であるが故に学問として確立する必要がある。それを部落学と名づける。
学問としての科学、文化は常にタブーに挑戦し、解決のプロセスを発見してきた。その意味で部落学は、日本人の社会のタブーの領域を解明し、その歴史と現代に、新しい視点を確立し、新しい文化の光をあてることになるだろう。
部落問題はこれまで、歴史学、社会学、民俗学、心理学などで研究されてきた。それぞれ一定の成果をあげているが、その段階で言えるのは、その対象に人が存在する意味において、あるいはタブーとしての差別が制度であった江戸時代にあっても、タブーの対象であった人々=部落民が、社会的機能を果たしていた、という意味において、その全体像を把握し、指摘することはなかった。
部落学は、そのような弱点を克服し、それぞれの分野の成果を糾合することで、全体像を把握し、新しい学問分野とする。
部落学とは、日本社会の歴史のなかで、主に、江戸時代の穢多身分を中心とする問題であり、そこから出発する。
これまで部落問題の研究は、しばしば穢多身分と非人身分を同時的に「穢多・非人」と捉えることがあった。しかしそれぞれの身分は構成の違いがあり、身分差別の構図も違っている。穢多身分は「生来のケガレ」などといわれ、ケガレを忌避=タブーとする観念の直接的対象になってきた。また「生来のケガレ」と言われた原因も、触穢意識という、他の身分には見られない観念的作用がはたらいていた。
非人身分にはこのような観念や作用がみられなくて、アウトサイダー的観念を持たれていた。そのため、両者を区別する。しかし、共通性もあるので、非人身分は共通する部分で説明する。
なお、ケガレを忌避する「忌穢」と、ケガレに触れた人もケガレとする「触穢意識」は、十世紀の「延喜式」で貴族の間の制度となり、戦国時代ころに大衆的になったと推定されている。
2、文化=価値を創った存在
これまで部落問題の教育は、差別の現実と、被差別体験、あるいはそれらの歴史や、差別を告発・抗議する運動の歴史と現実が中心であった。「差別から学ぶ」というのは、そうした傾向の典型である。次に、差別を解消するために、人権教育が重視されるようになった。
これらの動きは今も一定の必然性をもっている。現実の部落差別は、結婚などで今も根強いものがあり、告発・抗議がなければ、何もなかったかのように、闇から闇に葬り去られる可能性がある。
このような現実を反映したうえで、人権という概念も、人類の普遍的価値として、さまざまな現実・局面において検証されつづける必要がある。
しかし、他のあらゆる人権問題でも言えるのであるが、「人権を守る」と言っただけでは、何も解決していない。解決のために、人権が引き金になることがあるとはいえ、それぞれの課題の内部から、新しい認識や思想、それらに基づく具体的な動きや制度などが必要になるだろう。
そうした意味において、部落学は、部落問題の全体像の内部から、ことに、そこにあった生活と、生活を支えた仕事がもっていた周辺社会(農・山・漁村や都市)との関係性を抽出し、差別・排除の構図を見るだけでなく、部落が社会的機能として存在していたことを見る。
また、社会的機能としての仕事によって日本人の生活に必要なさまざまな文化を創り出してきた歴史を見る。こうした機能=仕事と文化を一つの概念で表現するなら、つまり、部落問題の全体像を、新しい視点として、一言でいうなら、その歴史は文明的存在であり、文化=価値を創ってきた、と言える。
部落学はこれらのことを明らかにする。差別=タブーを克服するプロセスは、古い差別的偏見に代わる、このような新しい認識・思想の構築によって示される。
一、部落学の時代的性格
すでに部落問題として、特徴的になっているが、差別を含めて、この問題の概要は江戸時代にある。したがって生活・仕事もその時代から見ることになる。しかも、別の意味で、そこから見るしかない現実がある。
江戸時代は、社会的機能としての仕事が明確だった。しかし、近代になると、身分や差別が制度的に廃止(一八七一年・賤民解放令)されながらも、旧穢多身分が果たしていた社会的機能=仕事がしっかり認識されることなく、その仕事を誰でもできるようにしておいて、旧穢多身分=部落民がその仕事から切り捨てられる。しかも、差別への救済策はなく、まるで何も無かったかのように放置される。これを「棄民政策」と私は呼ぶ。
棄民政策のなかで、差別だけは江戸時代と同じように結婚・就職におよび、旧穢多身分・部落民の生活は経済的に破綻し、都市ではスラム化するところが多くなる。その意味で、近代の生活・仕事は、分析・分類がむずかしく、あえてそれを考えようとすると、棄民政策の研究から始める必要がある。
しかし、棄民政策についても、ほとんど研究がすすんでいない。だだ、江戸時代の生活を見た結果からすると、棄民政策によって失ったものは、部落民の生活だけでなく、日本人の文化、なかでもそれを体系的に見る視点、あるいは精神の近代化の内在的手掛りが失われた。
近代になって日本人が失ったこれらを、私は「文化の空白」と呼んでいる。部落学はこの「空白」を埋めるものである。
江戸時代の穢多身分の仕事・労働から見ると、非人身分は、穢多身分の補助的機能である。
二、文明的存在
部落の歴史が文明的存在であったと言ったが、これは新しい認識なので少し説明する。
文明について「人と自然の関係にあって人が創った道具、装置、制度、あるいはすべてのシステム」と考える。人は初期的に海や山や野、あるいは田畑で食料の採取・狩猟・生産によって文明を創り出す。漁業・狩猟・農業などがその結果だ。
一方、人は自然の破壊的部分に触れて、医学などの科学を創り、あるいは危機管理装置を創り、さらには宗教などを創った。これらも文明だ。
日本も同じであるが、この国(大和を意味する。以下同)では古代より、自然の破壊的部分をケガレとし、忌避=タブーの対象とし、社会的身分の低い者、賤民階層がそれに触れ、対処する仕事をしてきた。江戸時代になってその仕事が穢多身分の世襲的専業になった。
さきに見た差別の構図(観念とその作用)からいうと、この仕事の世襲によって触穢が世襲的になり、触穢意識によって「生来のケガレ」とされ、世襲的に忌避=タブーの対象になった。
つまり、部落差別の構図はこの二つの観念、「触穢意識」とケガレを忌避する「忌穢」の観念連合からなる。これが部落差別の観念的原理である。
しかし、この仕事を文明的に見ると、自然のなかの破壊的な部分に触れる仕事によって、人の生活に必要な道具・装置・システムなどを創ってきた。また、そのなかで文化=価値を創ってきた。部落学はこの文明的要素を学問とする。次にこれらを具体的に見る。
三、穢多身分の仕事=「役」はキヨメ
全国に点在していた江戸時代の穢多身分には、一定の社会的「役」があった。社会的制度として規制された義務である。当時これを「御用」とか「役目」と呼んだ。そしてこの義務にたいして給与にあたるものが、金銭、または米・豆など現物支給があった。これが権利である。「役」は地域によって異なるが、全国の例を要約するとつぎのようだ。
水番、山番、牢番、警備役、街道守、斃牛馬処理、皮細工、刑場の労役、神社・仏閣のキヨメなど。
この要約は私が独自にしたものであるが、これらを裏付ける主な史料は、当時の穢多頭・弾左衛門が享保年間(一七一六~一七三六)徳川幕府に提出した「御役目相勤候覚」である。
そこにある「役」(役目)は「一、皮類御用之節、何ニ而茂差上相勤候(皮類ご用の節は、何にても差上げあい勤め申し候)。一、御尋者御用、在辺ニ不限被、仰付次第相勤申候(お尋者捜査は、周辺に限らず、仰せつけられしだいあい勤め申し候)」など十一項目に及ぶ。(『江戸社会と弾左衛門』中尾健次著)。
この史料を論評した大阪教育大学の中尾健次は弾左衛門の社会的「役」(役目)を分類して皮革生産と、仕置・断罪を含めた下級警察業務とする。
水番や山番は農村部の特徴であるが、警察業務の一環と考えてよい。神社などのキヨメは、祭礼にあたって境内の掃除とケガレ(動物の死体など)の処理と、「神輿」の先導をした。
これらの「役」は人の社会的生活にとって不可欠な仕事である。したがって私はこれらを社会的機能と考える。
この社会的機能は日本の社会全体で、一定の分類が可能だ。それはケガレを処理・再生する機能である。日本の民俗学では罪・犯罪がケガレであるのは常識だ。また人や動物の死・病気・出血がケガレとされてきた。神輿の先導は、観念の上で、日常の「俗」や「ケガレ」をキヨメ=払って「聖」なる空間を造った。
このように見ると、「役」すべてがケガレに対処し、それを処理・再生する機能であるのがわかる。日本ではこの機能を果たす作業を(儀式も含め)キヨメという。つまり江戸時代の穢多身分の「役」・仕事はキヨメ役だった。
十三世紀の風俗辞典『塵袋』に「キヨメをエタというは何なる詞ぞ」(『復刻日本古典全集』)とある。「エタ」「穢多」という言葉が初めて登場する文献であるが、この文献からも、穢多は本来キヨメと呼ばれていたことがわかる。
このような理由で、部落(旧穢多身分)の歴史に見る社会的「役」=仕事の総体を機能とし、「キヨメ役」の機能を果たしていたことがわかる。
また、江戸時代の身分呼称が「士・農・工・商」というように職業的カテゴリーで呼ばれることから、その下の賤民身分も同じカテゴリーで呼ぶことができる。「穢多」は「キヨメ」である。「非人」もまた仕事のうえで穢多身分の補助をしており「キヨメ」である。雑種賤民は呪術的芸能をふくめて芸事が多かったので「諸芸」とすればよい。
これは呼称の「言い換え」を意味するのではない。現代的認識として、私が提案していることである。穢多と非人を歴史的に区別するときは、カッコをつけて穢多又は非人とすればよい。
このように、歴史上のカテゴリーを通すことは、部落問題のみならず、日本人が自らの歴史を体系的、思想的に考察するために不可欠である。身分呼称のこうしたカデゴリーが無視されていたことで、見失なったものは多い。部落問題の難解さの一つの原因はここにある。また、日本文化に体系がないと言われる原因の一部も、このようなところにあると私は考える。したがって私は、以降キヨメを呼称として用いることとする。
また、文明的に見ると、ここに見る社会的「役」=仕事は機能として、文明的装置である。つまり部落の歴史は、文明的なキヨメの装置として、全国に存在したことになる。以降でそのことが明らかになる。
四、地域社会とキヨメの関係性
部落問題を差別・排除の構図だけで見ていると、大切なものが見落とされる。その一つが地域社会の関係性である。
キヨメ(穢多)村は全国で約六〇〇〇といわれる。その村は差別されるためにそこにあるのではない。キヨメ役(文明的装置)として、その機能を果たすためにある。そしてその村は、その地域で、社会的機能として具体的な関係性をもつ。
警察業務は典型的だ。キヨメ役は、その地域の警備・火の番など危機管理の予防的業務と、犯罪が起ったときに犯人逮捕にあたった。これは日本警察史のなかで常識だ。
山番は盗伐を防ぎ、農民の田畑を荒らす動物を追い払った。水番は、農業用水路の安全と、水の配分を管理した。
このように見ると、これらの仕事=キヨメ役が、農村のみならず、漁村、山村、都市など地域社会にとって必要不可欠な社会的機能であったことがわかるし、その一つが危機管理の末端・現場の業務であることがわかる。
このような機能を社会的関係性としてみる視点はこれまでなかっのであるが、キヨメ役への偏見と差別・排除の構図を克服するためにも、このような関係性をはっきり認識する必要がある。
またこのことは、差別の解消のみならず、日本人の危機管理意識の確立ために、見逃せない歴史的課題である。
現代、日本人の危機管理の欠落がたびたび指摘される。その原因がここにある。自然の、あるいは人為による破壊的な部分をケガレとし、それに触れないことに大きな価値を認めてきたのが、日本の貴族社会であり、後に大衆化し、部落差別の構図の原理になった。 そこでの貴族や大衆の心理は(今はほとんど下意識)、触穢意識によって、ケガレに触れると自分もケガレ、忌避=タブーの対象になる、というものだ。しかし、自然の破壊的な部分は避けられない。そのため、それに触れ、処理・再生する専業者をつくり、触穢意識によって忌避・差別の対象とした。言い換えるなら、危機管理の他人任せである。「あまえ」の構図でもある。
明治維新以後、近代社会がこの構図を内的に克服しなくてはならなかった。しかし、明治政府は、部落にたいして棄民政策をとり、警察機構=危機管理機構はバリやニューョークのそれを安易に模倣した。そこに危機管理としての「文化の空白」が生まれ、現代がある。
日本人の一人ひとりが、本来の危機管理意識を回復には、自分たちの歴史をしっかり把握し、それを内的に克服する努力が必要であろう。部落学はその端緒である。
五、斃牛馬の所有を考える
1 私有権を失う農民
これらの仕事=機能からさまざまな文化が生まれた。これを見ることで、日本文化全体に新しい視点、あるいは体系が発見できる。わかりやすい例は、斃牛馬処理だ。斃牛馬は、農民が飼育していた牛や馬だ。今はエンジンを持つ機械が動力として使われるが、その前は、江戸時代をふくめて、動力として牛馬が使用された。そのため、怪我や病気、死などで動力として使用できなくなると、処理した。これを斃牛馬処理という。
斃牛馬は動力としての使用価値を失っている。しかし、他の目的としては、まだ多くの使用価値をもっており、したがって商品価値をもっている。毛皮製品が代表的だ。骨・角・爪は装飾品など。毛は筆になる。肉食は一八七一年まで禁じられていたが、薬用として使われた。その他全ては熱処理されて肉骨粉として肥料になった。
これら使用価値、商品価値を農民が知らないわけがない。動力としての牛馬は農民個人の私有である。したがって処理後の価値も、本来農民の私有であるが、事実はそのようにならなかった。
ここに曖昧な構図がある。斃牛馬はケガレであり、農民は触れてはならないし、私有することができない。触穢意識があるからだ。したがって、斃牛馬は「捨てる」のが制度だった。キヨメ役はそれを「拾う」のが制度だった。そのため、基本的にキヨメ役にも所有権が成立しない。例外は多いものの、原則的にその所有は「お上」にあり、斃牛馬から生まれた毛皮などをキヨメ役が「上納」した。キヨメ役の仕事が「役」であり「御用」「役目」と呼ばれた理由がここにある。「上納」して残ったものが、キヨメ役の所有(原則としてキヨメの共有)となり、使用価値をもつ商品として流通した。
2 曖昧さと文化の空白
この曖昧な構図を原点に戻し、牛馬を私有していた農民から見ると、彼らの私有が代償もなく、あるいは主体的動機もなく失われていることがわかる。これは前近代の日本人の大きな特徴である。そしてこれが、近代的自我=個の成長に大きな障壁であったことがわかる。
なぜこのようなことになるのだろうか。問題なのは、そこにあった「曖昧な構図」であるが、そこにに部落問題があるのがわかる。つまり部落差別の原理としての二つの観念連合が農民一人ひとりの私有・所有意識を規制し、心理的作用をおよぼしている。
ここでは農民の牛馬の私有を通して考えているが、これは危機管理などを含めて、部落差別をしてきた一般的な日本人の心理や心の問題であり、ここで見る牛馬の私有と、その後の「曖昧な構図」によって、個の自立がないことがわかる。
しかもそれは、これまで部落差別の原理がわからないままであったと同じレベルで「曖昧さ」につつまれてきた。部落学はこの「曖昧さ」を克服する。
斃牛馬の私有を貫けなかった「曖昧な構図」は近代にどうなるだろうか。
ここに見る構図が廃止され、斃牛馬の取引が自由になるのは一八七一年である。この後、売買や流通は自由になるが、部落差別の原理を内部に持つ「曖昧な構図」は近代的に対象化されたり、克服されるのでなく、何もなかったかのように見過ごされる。棄民政策の帰結である。
とはいえ一方で、近代の皮革産業は「富国強兵」「軍国主義」をすすめる国家によって主導され、国家と結びつく政商が、欧米の技術を導入して大量生産をめざした。そのため経済の二重構造がここでも生まれる。
伝統的な技術を蓄積した歴史のなかの皮革産業は、零細企業として残るものの、「部落産業」といわれるほどに、さきの差別の構図のなかにとり残され、同じく農民など一般的にあった「曖昧な構図」の原理が考えられたり、意識的に克服されることはなかった。
これは日本人すべての精神的、文化的課題であるり、ここにも「文化の空白」がある。物質的、経済的文化だけは世界の一流であるが、心がともなわない現代日本人の姿も、こうしたところに原因の一端があると考える。
3 忘れられた「膠絵」
「文化の空白」としてもう一つわかりやすい例は膠(にかわ)である。皮や骨を煮詰めて作る接着剤だ。現代も細工物に使われているが、歴史的な美術作品の日本画に膠が使われるのはあまり知られていない。近代になって西欧から伝わった油絵は誰でも知っており
、絵といえば油絵と思われている。
膠は歴史的にケガレとしての斃牛馬から作られた。つまりキヨメ役が創った文化である
。そして、世界に誇る古い日本画の色の接着と保存に役だっている。日本画家は知っているし、今も使っている。しかし、この膠が日本人の教育に、正当に登場したことはない。
4 文化の体系を取り戻す
日本文化に哲学なし、体系なしと言うのは、日本の進歩的知識人が繰り返し主張したことだ。一方で、保守的な人は天皇制を軸とした国粋主義や国家主義を主張してきた。とはいえ、国粋主義や国家主義にしっかりした哲学や、文化的体系があるわけではない。ただ、進歩的知識人がややもすると、欧米(古くは中国)を軸にした発想を強くもっているために、反動的に国粋主義などが台頭する。最近の「新民族主義」もそのような流れにあるだろう。
両者のこの流れは日本史のなかで繰り返された。しかし、その繰り返しから生まれた新しいものはない。
その原因は、進歩派、国粋主義の両者が見落としているものがあるからだ。見落としたものは周縁の文化である。別の言い方をすると、日本の口承文化である。日本の大衆の多くは、明治初期まで文字を使わなかった。しかし、立派な文化を持っていたし、そこには一定の思想性や体系があった。これを見落としたら、日本文化の本質を失うことになるだろう。
芸能史を考えるとよくわかる。典型的に言うと、農産物の豊穣を願って行われる農耕儀礼(山村、漁村も同じ)が非農耕民によって都史に移動し、そこで新年の祝福芸・大道芸となり、それが歌舞伎など、現代の日本を代表する舞台芸能になる流れだ。
この流れに体系がある。しかし、祝福芸・大道芸を江戸時代などのキヨメ役や諸芸役(雑種賤民)が行っていたため、これを差別的に「乞食芸」と見、先の流れの一環として見ることができなかった。したがって流れのなかの体系も見出すこともできなかった。
農耕儀礼は呪術の世界であり、ジェームズ・フレイザーが抽出した共感呪術にあたるものが多い。農作業を類似的に表現する類感呪術・類似の法則(目的を達成するために、その行為を前もっておこなうと効果があるとする呪術)からなっている。この類似の法則は儀礼的な農作業の象徴表現であり、これは初期的な思想性を持っている。祝福芸・大道芸もおおむね類似の法則を踏襲する。しかし、歌舞伎舞踊などになると、類似の法則がなくなる。歌われる歌も儀礼的(作物の豊穣を願う)ではなく、人間の情感を歌う。ここに「神から人」への変化がある。呪術から芸術への変化でもある。
とはいえ、儀礼が持っていた象徴表現はつづく。歌舞伎の「様式」、能の「型」がそれである。ここには儀礼的象徴表現から芸術的象徴表現への変化を見ることができるし、思想的体系を見出すことも可能である。しかし、キヨメ役がおこなった祝福芸・大道芸をはずして考えると、その全体が見えない。部落学はその全体を再現し、考察するものである
。
具体例を一つあげる。農耕儀礼の「田遊び」は一九四〇年ころまで全国的に行われていた代表的な儀礼だ。米を作る一年間の農作業を、新年とか春、作業が始まる前に、一昼夜か二昼夜かけて神社の庭などで模擬的に演じる。豊作を願う儀礼であり、類感呪術である。
この中の単独の作業「田打ち」「柄振り」「鳥追い」「虫追い」などが独立し、模擬的に表現される儀礼もある。すべて、現代の文化人類学で言われる象徴表現である。
これら単独のものが、都市に運ばれ、新年の祝福芸・大道芸になるが、それは土地に縛られない非農業者によって運ばれる。その人々がキヨメやく、諸芸役であったが、芸能史ではこれらの人について、本来農民だっただろうと考えている。そうでないと農耕儀礼を身につけられないと思われるからだ。
こうして都市に運ばれた「田打ち」(春田打ちなど)、「鳥追い」などを演じる人は、門付芸人・大道芸人と呼ばれ、彼らの姿がそのまま、歌舞伎の舞台に登場し、「ご祝儀物」などと呼ばれる芸術的芸能になる。
この流れが日本の芸能史の太い流れと考えてよいが、門付芸人・大道芸人の芸を正規の芸能史からはずすことで全体像を失い、体系を失った。
まとめ(川元による)
立教大学では一九九七年から全学部を対象にした全学カリキュラムが設置され、そのなかで私は九九年から「人権とマイノリティー」という科目で部落問題を講義してきた。
とはいえ、私は、部落問題を差別だけで考えるのでなく、日本文化の問題として、文化全体のなかでこの問題を考えたいため、独自に「日本文化の周縁」というタイトルで講義をすすめた。
その間私は、部落問題を日本の学問の体系のなかにどのように位置づけるか考えていた。もちろんそのことは同時に、部落差別の発生や、その観念的な原理を解明し、差別解消を考えることでもある。また、部落問題の全体像をとらえ、それを日本文化全体のなかにどのように位置づけるか、地域社会との関係性をどのように捉えるかということでもあった。
二〇〇一年四月に私は『部落差別を克服する思想』という本を発表した。これは、部落と周辺社会との関係性と、部落差別の観念的な原理を実証的に解明するとともに、その発生史を仮説として書いた。
この本の原稿を書き上げたとき、私は部落問題を学問として立ち上げる内容に手応えを感じ、これを「部落学」とすることにした。
一方、立教大学では、二〇〇一年から、私が独自にテーマにしてきた「日本文化の周縁」を正規の科目にした。私は、その年から「部落学」を立ち上げたいことを学校側に言ったが、急にはいかず、「日本文化の周縁」のなかで、私独自のテーマとして「部落学」の講義を行うことになった。
これはまだ大学の正規の科目ではないが、日本で初めて、大学の、あるいは教育界に登場した教育のテーマであり、学問の領域である。
その年の四月、講義の最初の日、私は突然不安に陥った。「人権とマイノリティー」では二百人以上の受講生がいた。多すぎると思っていたが、しかし突然「部落学」としたことで、はたして受講生がいるのかどうか。
人権なら国際的な関心のなかにある。しかし、部落問題は日本人のなかでも関心が低いし、まだまだ重くて暗いイメージのなかにある。こうした状況のなかで、ストレートに「部落学」とした講義に現代の大学生がどれほどの関心をもつだろうか。受講生が一人もいないかも知れない。そんな不安だった。 「三人いたら講義になるだろう」そんなことを考えて教室のドアを開けた。そこには四、五十人の学生がいた。ホットした。その年の受講生は八十六人だった。二〇〇二年の今年は百五十四人である。どうやら、安定した講義になりそうだ。
また、「部落学」の講義を受けた学生が、ある高校に教育実践に行ったときの話を間接的に聞いたのであるが、学生の間でこの講義が「受けておいたほうがよい講義」になっているらしい。そうだとすると、私が目的とする講義の内容も、正面から受けとめられつつあるだろうと、思っている。
〔「部落学」は、アメリカ北イリノイ大学助教授・清水秀則氏との共同研究として03年10月米国中西部教育学会(MWERA)において研究発表。04年に同学会機関誌にBURAKU GAKU(BURAKU STAD
