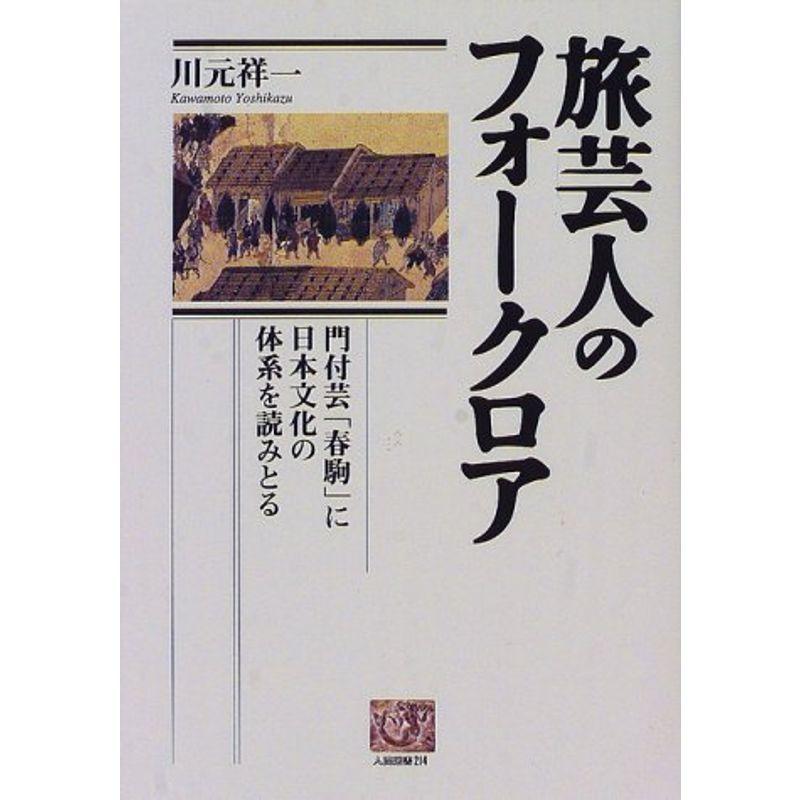
この国の近代を問い直す―主体の革命 <上>
川元祥一
はじめに
日本人の精神の漂流、空白が指摘される現代、われわれは明治維新以降の日本の近代化を問い直し、その指導的思想であった脱亜入欧と、絶対的天皇制としての国家主義をきちんと反省し、それらにかわる新しい文化機軸を発見すべきと考える。
諸外国との交流や相互の影響を否定するものではない。むしろ積極的に考えたい。しかしそのことによって、自分たちの歴史や伝統を軽視したり、無視してはならない。仮に、諸外国に較べて自分たちの文化が低いと思われる場合、それを自分たちの想像力によって変革する努力をすべきだ。そしておそらく、そうした努力によつて、この国に住む者の文化的コンセンサスが生まれると思われる。日本の近代化は、こうした努力を放棄し、欧米の努力によって生まれた文化的成果を、主に国家・権力を通して導入したのである。このような状態で文化的コンセンサスは生まれないだろう。それだけでなく、このような状態から、文化は外から、あるいは「お上」から、あるいは外国語ができるインテリ・文化人から与えられるものという、ほとんど無意識の文化構造が敷かれることとなり、自らの想像力と、紆余曲折の努力を軽視したり無視する傾向が生まれるし、それが空白に繋がると思われる。
この傾向は、維新以降百数十年の間徐々にすす進み、現代頂点に達しつつある。テレビや新聞などの論調だけでなく、子ども向けの教育番組の、ちょっとした背景や衣装にも、造形や価値基準を外国に求める傾向が強くなっている。それだけでなく、想像力を欠いたとしか思われない凶悪事件なども、決して無関係でないと私は考えている。
この傾向を内在的に克服しなくてはならない。一人ひとりの主体的想像力、あるいは批判力は、その克服の過程から生まれるだろうし、改革する人も保守的な人も含めた文化的コンセンサスも、そこから生まれるだろう。
一 主体の革命
大江健三郎は、日本人の精神が西欧の模倣と、自分たちの伝統の間で、あいまいに二極分解している、と観察した。的確だと思うが、その病理はさらに進んでいるのではないか。
日本国憲法の改定を課題にした憲法論議の中にもそれが現れる。この憲法が、戦勝国アメリカの押しつけだとする論者は、日本の伝統を重んじるものにしょうと言う。具体的には、現憲法が個人の自由や人権を主張し過ぎているとし、愛国心や道徳、あるいは非常事態での自由の制約などに重きを置こうとする。反して憲法の平和、人権、民主主義に重きを置く者は、国際的な「普遍原理」を尊重する。個人あっての国家か国家あっての個人か、という二項対立の構図でもある。あるいは伝統か国際的価値かという構図にもなっている。
こうした二項対立の構図の間で、中間的発想と言われるものがある。例えば「愛国心」だ。アメリカ人は、九・一一後の戦争に反対する人も、愛国心から反対する。しかし、日本では、こうした愛国心が語られることがほとんどない、と言うもの。私は「伝統」もそうだと思う。伝統と言えば天皇制・国家主義に繋がると思われがちだが、それが間違っている。伝統もいろいろで、洗濯の余地がある。
私はこのような憲法論議の中に、精神的空白(私はこれを文化の空白と呼んできた。拙書『文化の空白と再生』)の特徴があると思う。本来なら、ここでいう中間的発想は、中心的発想でなくてはならない。例えばこうだ。国際派が主張する国際的「普遍原理」、そこでの平和、人権、民主主義は外国の例だけでなく、日本の歴史や伝統の中から語られるのが、本来の姿だからだ。そのことによって、その普遍的価値が、この国の人々の共有となり、コンセンサスとなる。
こうした本来の姿に異論を唱える人は少ないと思う。問題は、それを語る歴史・材料がこの国にあるかどうかだ。私はあると考える。少なくともその芽はある。その材料・芽を育てたり、抽象化する努力を、今からでもすべきだ。
それをより具体的に言うと、脱亜入欧と国家主義を反省し、新しい機軸を創造することだ。これを「主体の革命」と呼ぶこととする。憲法論議の中で言うと、国民統合の象徴としての天皇とその制度にかわる、新しい国民的コンセンサス、文化的機軸を、国家や権力からではなく、民衆史あるいは人々の生活の中に見出すことだ。私はこれを、国家主義に対抗する民間主義と呼び、背景の文化を民間文化と呼んでおく。
二 民間文化
民間文化がどんなものか示すため、一つの手掛かりを言うと、明治維新後その政権によって弾圧されたり、禁止されたりして、日影におかれたもの、あるいは差別観によつて、その価値がまったく認められることなく排除され、消されたものである。
これらは近代の学校教育には登場しない。マスメデアにも登場しない。とはいえ地域社会では根強く伝承されている。大江健三郎が言うこの国の伝統的なものはこうしたものだろう。代表的なものの一つは、祭りや年中行事である。これらは、近代では国家神道の一部として国家主義的に把握されてきた。今もそのように思っている人が多いかも知れない。しかし、それらの中には、本来国家と関係ないものが多い。また神道以前の、自然との共存を図るアニミズムも多い。田遊や田植踊り、鹿踊りなどなどだ。これらは国家や権力が創ったのではない。海、田、山の自然を対象に働いてきた人々が創った。天皇制信仰は、これらの上に乗って、奪略しただけだ。
もう一つ、これまで誰も気づかなかったものがある。後で詳しいことを言うが、江戸時代の穢多・非人身分の者は、自然の破壊的部分=気枯れに触れて文明・文化を創ったのである。この気枯れ(穢を民俗学でこのように表記する。これが正しい)をカオスに置きかえると、私が言うことが簡単に理解出来るだろう。すべての科学・芸術などはカオスに触れて生まれる。日本の江戸時代は、穢多・非人身分がそれを行ってきた。私はこれを部落文化と言う。また、穢多・非人身分の職業をキヨメ役と言う。
部落問題は、これまで差別に焦点が当てられたが、部落文化の認識によって、差別的偏見が越えられるだけでなく、その認識が、これまでの日本文化論、なかでも天皇制と神道観を根っから転換する要素でもあり、主体の革命の主軸となるものだ。
民間文化が、人の生存に必要不可欠な要素として生まれ、創られたのがわかるだろう。これらは本来、国家と関係なく、自然の恵みや破壊・生死を対象に生まれ創られた文化である。その意味で、この文化は、国家の違い=国境とは関係なく、自然の違いと共通性によつて色分け・区分できる。そしてそこに、個人か国家かという二項対立を超える、新しい文化軸が見える。例えば「愛国心」を越える「文化圏」などだ。
三 口承と多文化
この国の民間文化は大きく分けて三つの個性と、一つの共通性を持つ。
三つの個性とは、沖縄、アイヌ、和人の歴史と文化的個性である。日本の近代は、絶対的天皇制によって沖縄とアイヌの個性を踏みにじり、差別した。この近代を反省し、あらためてそれぞれを大切にし、多文化主義のもとで、その総体を日本文化と呼ぶべきだ。私はこれを列島文化と呼びたい。このような把握によって、民間文化の要素と可能性がよりはっきり見えてくる。
一つの共通性とは、それぞれが口承文化として発展し、高い文化水準を持っていたことだ。
しかしここでもまた、日本の近代が、文字文化を重んじるばかりに、口承文化を蔑視、無視、差別した。私は文字文化を軽視する者ではない。その優れたところを重んじる。しかし、だからといって、自分たちの歴史や文化の基盤にあったものを蔑視したり、無視したり、差別してはならない。
明治初期の学制制定が国民皆字制であったのは知られている。それはそれでよかったと思うが、その時、それまで分厚く存在し、人々が共有していた口承文化を検証・継承し、学校教育などに生かすべきだった。しかし、今だにそれがされていない。
文字文化による口承文化の蔑視、差別は奈良時代の貴族の間から始まった。中国から伝来した文字を当時の貴族が獲得し、ステータスとしながら、民間の口承文化を無学文盲の文化のように見た。この頃から、文化は「お上」からといったような構図が敷かれた。近代の脱亜入欧を含め、その構図は今も続いている。だが、それは大きな誤謬だ。空白の病理の原因の一つでもあると、私は考える。
民間文化の基盤に口承文化があるのがわかる。そして、この口承文化と部落文化を主軸に、日本の近代を超えるブロセスを描くことができる。それは「脱亜入欧」を克服し、アジアと共生する文化軸でもある。
この国の近代を問い直すー主体の革命(中)
川元祥一
一 危機管理
護憲か改憲かというと、私は一条を中心とした天皇条項を廃止し、新しいコンセンサスを主張する改憲論者である。
憲法論議では九条が話題になることが多いし、交戦権の否定や、国際問題の平和的解決を主張するその思想に賛成であるが、近現代のこの国の歴史を前提とした場合、そして、主体的で自主的あろうとするときは、何よりも第一条を問題にすべきだ。九条の交戦権の放棄などは、その前の戦争を反省することでなりたつのであり、そうである以上その戦争を精神的に主導した天皇制もきちんと反省すべきだ。戦前の天皇制と戦後憲法のもとでのそれは制度として異なっているものの、その地位が世襲であることは戦前と変わらないのである。こうしたことをきちんと反省すべきだ。
こうしたことを前提に言うのであるが、残念ながら、今の国際社会や人々の生活からして、危機管理機構は必要と考える。その場合当然、今の自衛隊や警察をどのように考えるかという課題が生まれ、その規模などが直面する話題になると思うが、この国の住民にとって、つまり私たちにとって第一義的に重要なのは、そこでどのような国家観、国民観が語られるか、ということだ。
そこで語られる内容は、どこかの国を参考にすることがあるだろうとはいえ、基本になるのは自分たちの軍隊、警察の歴史をどのように考えるかだ。そこに主体とか自主の基本がある。そして、そこにコンセンサスの芽がある。コンセンサスとは、与えられるものではない。自分たちの歴史、生活から発見し育てるものだ。
そのことによって、誰にでもわかる透明な危機管理機構を育ることができるだろう。今の自衛隊はそうしたことが不透明だ。
日常の危機管理としての警察も、私たちの歴史から断絶しコンセンサスを失っている。江戸時代までの警察機構の現場は、私が言うキヨメ役が担っていた。明治維新後、脱亜入欧によってパリやニュヨークのそれを模倣し、現場のキヨメ役を一方的に解雇したのである。ここには強い差別観もあった(拙書『部落差別を克服する思想』)。
もちろん近代と前近代の機構や人材が異なるのは当然だ。しかしその場合、前提となる歴史を総括し、変革のプロセスを明確にしておくべきだ。この国の警察機構は、そして脱亜入欧で導入された多くの文化は、このブロセスを失っている。それが心の空白、文化の空白に繋がっているだろう。
歴史的前提なく作られたこの国の近代警察機構が直面した困難は、犯罪者を追捕する現場のノウハウを持たなかったことだった。そこでそれを補うために、やくざに「水先案内人」を依頼し、取引をした。これは日本警察史で常識なのだ。そして、それが現代に尾を引いている。
ここに、危機管理機構の不透明さの最たるものがある。これらを透明なものにし、常に責任者が明確であり、かつその責任者が国民の選挙で交代できることが必須条件である。これが主体的で自主的な普遍的価値というものだ。
二 自分たちの歴史
憲法の平和・人権・民主主義も同じことがいえる。
この普遍的原理について次ぎのような考え方がある。「日本でも憲法に書き込まれた近代的原理がすぐ実現したわけではない。日本の伝統的価値、習慣などとの緊張関係、せめぎ合い、対話の中で共存しながら徐々に定着していった」(『朝日新聞』四月二九日)。 現実的経過としてこのような記述に疑問はないかも知れない。しかし、その現実に決定的な欠落がある。また、その現実は「定着」とは言いがたい。
大江健三郎の言う二極対立がここにもあると思うが、私はこの対立が「共存しながら」「定着」しているとは思えない。そのせめぎ合いに「空白」を感じるのである。それは「上」から押しつけられるものに似ている。
こうした「空白」を克服し、定着するためには、自分たちの歴史の主体的革命が必要と考えるのである。
この普遍的原理・思想がヨーロッパで生まれたのは知られている。どこで生まれても、学ぶへきものは学びたい。とはいえ、そこで学ぶべきは、出来あがったものだけでなく、それを生むプロセスが大切と考える。ヨーロッパでそれが生まれる過程では、人々の血と汗が流された。私たちも、私たちの歴史を前に、血と汗を流そうではないか。その過程にこそ、本物のコンセンサスがあり、主体とか、自主性がある。
保守的な人がいう愛国心や道徳、あるいは自由や人権の規制は、この国の近代でも何回も言われたことであるが、その結果はほとんど閉鎖的だったのではないか。とはいえ、保守的な人の中には「空白」を感じ取り、それを克服しようとする人もいるようだ。そうした人に、そして革新的な人も含めて言いたいのは、この国の文化の底力は国家や権力にあるのでなく、民間にあるということだ。そして、その民間文化は、この国の場合、文字に書かれたものが少なく、むしろ文字文化によって軽視・無視・差別されてきたということだ。その具体性を示すが、まずここでは、平和・人権・民主主義の内在性を示したい。
三 内在の普遍
このようなことはすでに指摘されていると思われものの、憲法論議ではあまり見られないような気がしている。
憲法がどこまで自主的か論議があるとしても、その前の戦争を反省することで制定されたのは誰もが認めるだろう。その反省は制度としてだけでなく、実態としても考えるべきだ。そしてそこに、内在的な平和の運動と思想がある。典型的なのは広島・長崎の平和運動だ。沖縄の反戦運動もそうだ。こうした民間の動きを見るなら、平和の思想がヨーロッパで生まれたとばかり言えないだろう。その思想は地域性ではなく、人々の血と汗の中から生まれる。そのことを重視しよう。
こうした指摘を「こじつけ」とし、すくなくとも憲法の「平和」の原理はヨーロッパから、と言う人がいるかも知れない。もしそうなら、憲法の自主性が損なわれるのであるが、損なわれても普遍的であればいいと言う人もいるだろう。こうした意見が多いのだ。が、もしそうなら、広島・長崎・沖縄も普遍的なのだ。そしてその場合、憲法をより「定着」したものにするため、自分たちの歴史から語った方がいい。
人権も、外から入ってきた概念であり言葉ではあるが、そのために血と汗を流した歴史はこの国にたくさんある。その代表的なものは江戸時代からの身分差別、今の部落差別との戦いである。近代社会なってからの水平社の闘いは言うまでもないが、私が特に注目するのは、身分差別が制度的であり、すべての人がなんらかの身分的規制をうけている時代に、その規制や差別と戦ったキヨメ役の歴史である。こうした闘いでは、多くの犠牲者がでた。多くの血と汗も流された。
江戸時代末期の岡山藩で起こった「渋染一揆」と呼ばれるものは、藩がキヨメ役に対して着物の色を渋染と藍色に規制しようと、お触をだしたのであるが、その規制に反対し、直訴を起してお触を撤回させたのである。
ほとんど同じ時期に、武蔵国寄居では、鼻緒を市場で売る権利が幕府によって奪われようとした時、権利を守るために八州取締役を虜にし、幕府と対決したキヨメ役の闘いがある。闘いは負けたが、その権利の主張は、岡山のそれも含めて近代的である。
また、アイヌの人権の闘いもある。その権利は「旧土人法」を廃した「アイヌ新法」に結実した。
民主主義の典型的例を示す。新潟県(旧柏崎県)栃尾市では、明治初期に庄屋の世襲を廃止し、選挙で選ぼうと一揆が起こり、成功した。そして、一揆を伝える「ちょんがれ節」が創られ残っている。「ちょんがれ節」は江戸時代末期から政治の腐敗を批判・風刺して幕府に弾圧された近代的文化なのであるが、近代の明治政府からも弾圧されて、民衆は「浮れ節」と呼んで歌い、やがて「浪曲」になる。「浪曲」が批判的精神を失うのは、政府の富国強兵の圧力からである。
この国の近代を問い直す―主体の革命(下) 川元祥一
一 八月の論議
毎年八月十五日になると閣僚の靖国神社参拝が問題になり、毎年いつも同じ論議が繰り返される。戦争責任者とその犠牲者を一緒にしてはならないことから、その祭祀に大きな疑問がある。また、神道としての祭祀は信仰の自由の上で、整合性を失っている。
一方小泉首相は、アジア諸国からの参拝批判に対し、自分の国の文化を大切にするのがどうして悪いと言うが、それをなら、侵略によって他国の文化を踏みにじった歴史をきちんと反省すべきだ。そうした姿勢によってその言葉に普遍性が生まれる。そうでない以上、この国の近代の前でその言葉は偽善であり、その偽善が空白に繋がる。青少年の心の荒廃を思わす事象の原因が教育や家庭に求められるが、深層ではこうした空白が原因と思う。大人も子どももコンセンサスと想像力をともなう精神的指針や価値を失っていると思うからだ。
もっとも、繰り返される論議は表層的であり、靖国神社の深層に触れていない。深層に触れた論議がないのが不思議であるが、保守、革新を含めて、自分たちの歴史を忘れたり無視する傾向がここにもある。そしてそこに空白の真因があるというべきだ。この空白を埋めるべきだ。靖国神社でいえば、そうすることで論議はまったく違ったものとなる。
二 戦争か革命か
戦争犠牲者の「霊」が祭られている。これが靖国神社の神社たる由縁であるが、どうしてその資格があるのだろうか。それは、神社の形があるからではない。その資格として、この国の伝統的文化、あるいはその思想性がある。それは神社の祝詞に表現される。その理由を細かく書く紙の余裕はないが、この国の多くの神社が神格化されるのは、祝詞にある思想性であり、それは呪術である。
良かれ悪しかれ現状では、古事記などにある古くからの呪術が、多くの神社祭祀の思想性であり、これを神道と命名したのは後のことだ。この呪術を細かく分析・分類をすることで、新しい機軸が発見できると考える。
祝詞は古事記などの神話をもとに長々と続く。靖国神社のそれも同じであるが、古典文学研究の中で祝詞の思想性がどんなものか指摘されている。その思想性は「このようにありたい」とする願いを象徴的に唱えることだ。世界的水準で言えば言葉の類感呪術(類似の法則)である(豊田国夫『日本人の言霊思想』)。靖国神社のその部分を見る。
「去し歳の正月三日には、伏見役に奉ろはぬ臣等を拂ひて、西の京を静め、五月の十五日には忍岡に屯集ひて、たわ事議る賊をほふりて、東の京を治め、九月の二十二日には若松の城を討ちて陸奥を平げ、今年の五月の十八日には筥舘の塞を征きて國中悉く掃ひ清め、まつろへ果てし中に、此の四日は殊更に功を立ぬる日にし在れば、後の世に偲ひ行かむよと、毎歳に此の日を祭の日と定めて斎ひ…」(『靖国神社百年史』例祭祝詞)。
一八六八年の鳥羽伏見の闘いから函館の役までの内戦を政府側から述べるのであるが、明治維新を近代革命とするなら、これは武力革命の仕上げをリアルに語っている。そして、これを祝詞の思想性に照らすと、武力革命の勝利を称える革命歌であり、その神社は犠牲となった革命戦士の魂を迎え称える革命記念館と言えるものだ。
革命戦士を称える方法はいろいろあるが、この国の伝統的文化としての祝詞の本来の意味からして、靖国神社の性格はこれ以上でも以下でもない。ましてや、神格化された祝詞の意味からして、その後の外国との戦争や侵略とまったく関係ないものだ。
保守派はこうした思想性を誤魔化し曖昧にしている。革新派は直視しようとせず頭から否定的に見て、国際的普遍性を持ち込む。そうした傾向が続いていると思う。そしてそこに空白が生まれるだろう。私は、ここにあるような呪術の世界を克服し、内にある思想性をより普遍的なものにする努力をすべきと考える。それが主体の革命である。
三 部落文化から
私が祝詞の思想性などに気づいたのは、部落問題からだ。部落問題は差別だけ見ていたらその本質や解決の道筋が見えない。そこには特徴的な文化があった。それが見えなくなったのは近代になってからだ。先に言った、この国の近代の特徴に原因がある。その文化を再発見することで、この問題にふくらみが生まれ、根強い偏見や差別を超える道筋が見えるとともに、天皇性とは違う民間文化を主軸にしたコンセンサスが見えてくる。
部落文化の中に、全国各地で家々を廻り新年を賑わした門付芸というのがあった。三河万歳などが知られている。今も芸を伝承する所があるし、私は十年前から東京・向島でそれを復活させ、協力者たちと演じている。
門付芸は「神」として迎えられた。その「神」の資格・思想性は祝詞と同じ類感呪術であり、言葉や身体表現、絵によるものである。例として、向島で復活している「春駒」という門付芸の歌(言霊・私はこれを言寿と言う)の一部を見る。これは絹で富を得る養蚕事業の全過程を歌う。それが「このようにありたい」とする呪術的類似の法則によつて「神」とされる。
「…蚕飼いにとりては美濃の国や…尾張の国で採れたる種は、さても良い種や…とほめよろこんで…飼い女のおん女郎衆にお渡し申す…右の袂へ三日三夜…左の袂へ三日三夜…六日六夜を暖め申す、暖め申せば温め申す…三日に水もち四日に青む…」(拙書『旅芸人のフォークロア』。
蚕の種・卵を人肌で六夜暖め、卵が青くなって蚕の幼虫が孵化する過程を歌う部分だ。この後桑を食べさせ、繭から糸を採り絹にして売るところまで歌われる。祝詞と同じ思想性なのがわかるだろう。
こうした思想性は天皇の国家祭祀としての「大祓」から各地の神社、そしてさらに基層にある農耕儀礼や漁労・狩猟儀礼(これらを私は労働儀礼と呼び、基層文化と呼ぶ)、部落文化に貫かれている。しかもそれらは、国家祭祀が先にあったのではなく、自然に直面し食料を獲得した基層文化が先行したことが科学的定説なのだ。
このような科学的定説を基にすると、天皇制や神道一色に塗りつぶされていたこの国の伝統的文化、呪術の世界をシャーマニズムとアニミズムに分類・区分できるのがわかる。世界の呪術を分析したフレイザーは、呪術の中に自然の法則に依拠した部分があるのを早くから指摘しているが(『金枝篇』)、アニミズムがその部分に当ると私は考える。
鯛を釣ってニッコリのエビス像は、鯛を魚介の富の象徴とする類感呪術の「神」だ。その「神」が、類似の法則によって富を集める商業の象徴となった。この「神」としてのエビス像を人形に変え、浄瑠璃で操作したのが人形浄瑠璃であり、文楽なのだ。ここには「神から人」への変化がある。ところが、室町時代に文字文化を身に着けていた貴族が、中国から伝来した傀儡と混同して記述したため、文字文献を一級資料とする後の研究者がエビスや人形浄瑠璃を中国伝来とする傾向が続いた。これと同じ傾向が文字をあまり使わなかった基層文化、部落文化を見る目に多い。
四 文化軸と体系
以上のような指摘の中で、新しい文化機軸、コンセンサスをどう考えたらいいだろうか。結論を言うと、これまで文化軸として考えられなかった部落文化をこの国の文化に取り込むことでこの国(和人として。以下同)の文化の全体像が見えてくる。その全体像によって始めて文化の体系とか抽象が見えるだろう。その全体像を概略すると、基層文化が自然の富を対象とし、部落文化が自然の破壊的部分(気枯れ)を対象とした。天皇制はそれらと外国のものを権力的・権威的に集約した。
思想がない、体系がないと言われた日本文化である。たしかに言葉や文字で抽象されたものはないだろう。抽象化は文字文化によってより可能性を持つと思われるのであるが、この国の文化にはこれまで文字や言葉にならなかった体系がある。それはいま言った文化の全体像によって始めて抽出できる。つまり部落文化を取り入れることで始めて抽出できる、と言える。
その一つの例は、祝詞や門付芸で見た言霊・言寿の思想性とその変化である。言霊・言寿は古事記や万葉集にある。日本書記に描かれる「田舞」は農民の米作りの身体表現・象徴としての類似の表現、「神」だった。
かっての国家祭祀を含めた祝詞、あるいは神道、あるいは基層としての労働儀礼も含めて、これらは古くから現代まで、同じことが反復されている。むしろ変化のないことに価値を置く傾向が強い。そうした反復に体系はないだろう。体系は変化から生まれる。そして、その変化を部落文化が実行した。
祝詞と同じ世界にあった「春駒」は呪術的「神」を脱して人間の物語を歌う歌舞伎舞踊になる。「神から人」の変化であり、その流れ、変化の中に体系を見出すことができる。エビス像から文楽への変化(これは農民)も同じだ。ほかにもたくさんの例がある。それら体系の集約が、新しい文化軸になり得ると私は考える。
<おわり>
【「アソシエ21・ニューズレター」6・7・8月号掲載】
