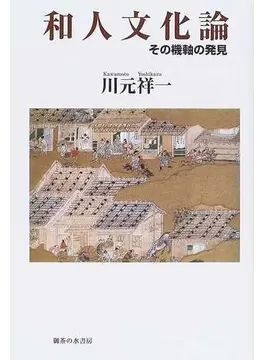
花見の風俗・その発想と体系--『和人文化論』より抜粋
日本文化に、口承文化と部落文化といえるものを織り込むと、この国の伝統文化の変革と、そこにある体系と思想がみえてくる。それはこれまで誰も語らなかった日本文化論である。別の言い方をすれば、歴史の上の社会的上部と底辺の全体像を把握することによって、初めて本格的な文化論が抽出来るということであろう。同時にそれは、そこに見え始める文化的体系と思想は、この国の社会的、文化的要素として問題とされながら、答えが見つからず、未解決といわれていた部落問題、とりわけ今も根強い差別を一人ひとりのなかで克服する道筋を描くことでもある。この問題は、差別の対象である少数者としての部落民の問題ではなく、古くて非合理な差別を知らぬ顔をしたり、他人事のようにふるまってきた日本人一般の、深層心理ともいえる問題だったのだから。そしてその深層を解くことによって、当然のように、この国の見えなかった伝統と新しい未来が見えてる。
日本文化に哲学なし、座標軸なしとする声が常識のようにいわれる。だが、それはどうやらまちがいだ。これまで多くの思想家や研究者が手掛りにしてきた文献資料を離れ、この国の風土、自然の中で直接狩猟・採取・生産の現場で働いてきた入々の、その風土や目然に対応した文化をみると、そこには明らかに一定の法則があり座標軸といえるものがある。そしてそれは哲学的・思想的思考の母体として十分耐えうるものであろう。事実、ながい歴史のなかでその法則やそれをもとに形成された座標軸といえるものは日本人の生活のなかに様々な風俗や文化的思考・形象を生み、しかも多くのものは文化革命ともいえる変化をもたらし、現代にいたっている。なお、この論文での日本人は厳密には和人を指す。アイヌ民族や沖縄には強い個性をもつ文化が認められるからだ。ただ、文化的に〃和人文化〃という言葉が定着していると思えないので、「日本(和人)文化」と限定したうえでこの言葉を使う。
最初に風土や目然・宇宙に対応した狩猟・採取・生産活動のなかに、人々の願望や感謝を込めた一定の観念としての法則が生れた。そしてそれをさまざまに応用した文化的体系が生まれるのであるが、多くの場合それは政治的権力の発生とともに、自然からは外れ、権力の補強装置としして使われる。日本(和人)の場合その傾向が強く、そのため人々は目分たちの狩猟・採取・生産活動から生まれた文化に関心を持つことが少なく、いっそう政治的権カとして天皇制、国家祭祀、神道、さらには国粋主義の装置として衣装をつけられ、使われてきた。
しかし、人々がその土地の風土や自然、宇宙に向って観念し、形象してきた文化は本来は自然観、宇宙観につながるものであって政治や権力と直接には関係ない。したがって、私がこれから指摘しようとする働く者が創ってきた文化の法則や座標軸は、長く同一視された神道や天皇制、国粋主義などと区別する作業であり、区別しないかぎりそれは見えてこないだろう。
一方、これまでながいあいだ多くの思想家や研究者が様々なアプローチをしながらも、日本文化に哲学や思想の体系、あるいは思考の座標軸がないとしてきたことは、現代の日本人の心の状態にとって、決して良い要因ではないし、少なからず悪い傾向、あるいは「不毛な傾向」を生む要因になっていると思う。
もちろん哲学的、思想的体系や軸がないといっても、そこではそれなりの抽象はある。日本人の心の状態を”和の精神〟などというのはその典型だ。また、たびたび天皇制が日本文化を代表するかのようにいわれるのも、その抽象の変形だ.、しかし、そのようにいっても、そこに何か普遍的な思想や座標軸・体系は抽出できない。
古代からの中国や朝鮮、あるいは近代における欧米からの影響も大きい。私は今、ある大学で講師をしているが、学生たちと日本文化について話しあってみることがある。若い彼らの考えは微妙な違いを個々にもつとはいえ、概括すると「日本人は自分で創った文化はないけれど、外国から入ってきた文化とうまく調和して目分のものにしている」といった考えに代表されると思う。そして、おそらく中学校や高校でそのように教えられるのだと想像する。
もちろん外来文化を否定したり排除する考えはない。私は多文化主義の立場に立つ。異文化の存在を認め、それぞれの交流が豊かさを産むことを認める。とはいえ、そうした多文化主義の立場をとりながらも、自己の文化の思想的体系や座標軸をもたないというのは、現代のように情報機能が極度に発達している時代は特に、それが精神的によい方向に向う要因になるとは考えられない。グローバル社会が強調される現代ではあるが、自分の伝統や歴史を無視したり軽視することではない。自分たちの伝統や歴史を大切にしながら、それらが内包する体質をより普遍的なものに変革する努力こそ、グローバル社会の必要条件と思う。その努力の中に、結果としての形象や抽象だけでなく、人間としての寛容や味わいの琴線が生まれると思うからだ。
直接的ではないだろうし、それを証明するのはむずかしいかも知れないが、青少年による凶悪事件がつづく昨今、あるいは「学級崩壊」といわれる荒廃した心の状態など、さらには青少年だけでなく大人社会での不正や腐敗、凶悪事件など、このような状況に対して日本人の心の空白が指摘されることがよくあるが、そうした心の空白は思想体系や座標軸を失ったとされる文化的状況と無関係ではないし、根っこで両者は深い関連をもつと私は考えている。
人々の会話にしろ議論にしろ、あるいは生活の諸相にある個性の違いや競争の結果など、人々は差異を差異として認識する前堤として、一定の共通認識(議論のための共通の認識や、競争を成立させる一定のルールなど)を必要とする。その共通認識がなければ会話も対話も成り立たないし、競争はとどまるところを知らない争い事になってしまうだろう。
これまで日本文化の中に哲学や思想の体系や座標がないといわれ、人々がそのように思ってきたということは、このような共通認識を欠いていることを意味してはいないだろうか。しかも、視点を変えれば存在するかも知れないそれらを、これまで誰も指摘出来なかったとすれば、人々は何か大切なものを感じ取りながらも、共通認識や共通の場を失って心の漂白を重ねてきたのではないか。そしてだからこそ一方で、たとえそれが表面的で擬似的であっても、何かの画一性を求める傾向をもつのではないか。(略)
なお、この論文での日本人は厳密には和人を指す。アイヌ民族や沖縄には強い個性をもつ文化が認められるからだ。ただ、文化的に〃和人文化〃という言葉が定着していると思えないので、日本(和人)文化と限定したうえでこの言葉を使う。(略)
一、 花見は生命力再生の呪術から
日本(和人)文化の中にある労働から生まれた文化と、その法則がどんなものかあらかじめ知るために、現代も人々に親しまれている事例を一つ取り上げる。
花見は、日本人の春の風俗として今も盛んだ。ますます盛んになっているといってよい。この花見は、桜の花の下で酒を飲んだりご馳走を食べたり、歌ったり踊ったりと、今では特別意昧のない娯楽になっているのであるが、これは本来、春先の山で若い芽や花をつけた樹木を見、そばにいて愛でることで、その若い芽や花の新しい生命力を自分のものとして身体に受けようとする人間の願望が込められており、古代社会では呪術的儀礼の一つであった。『日本風俗史事典』(弘文堂)では、古へから桜を中心にした花見が盛んだったとしながら「桃山時代から江戸時代にかけて花見はいよいよ盛んとなり(略)都市の花見が早くから行楽化したのに対して、農村では三月節供、卯月(陰暦四月)八日など春の初めの特定の日に、山野に遊び、花見や花摘みをする風があり、これを花見正月などと呼び、農耕儀礼のひと⊃として行なわれた」とする。
ここに農耕儀礼という言葉が出てくる。現代では一般的にあまり使われないし、聞き慣れない言葉なのかも知れないが、日本の伝統的文化、あるいは民俗学のなかでは今でもよく使われるし、農村では今でも生きた言葉だ。『大辞泉』(小学館)は、農耕儀礼を「豊作を祈って行なわれる儀礼・祭事・予祝儀礼から収穫感謝祭に至るまで、農作物の成長段階に応じて営まれる一連の儀礼をいう」とする。なお、「予祝」とは労働(作業)に着手する前にあらかじめ前もって豊作・豊漁・安全などを労働の対象に向って願っておくこと。「感謝祭」はその結果へのお礼である。日本の農・山・漁村で行われる労働の儀礼は主にこの二つから成り立っている。春に行われる花見はそのうち予祝にあたる。
私たちが春になってなにげなく見たり、あるいは参加して盛りあがる花見は、本来このような意味をもっていたのである。そこでその本来の姿がどんなものであったか、そしてなによりも「花見」という行.為がなぜ農耕儀礼で、農作物の豊作を前もって願う「予祝」にあたるのか。そこにどんな心理があり、どんな社会的機能があったかを古代文化を通してみていきたい。そして、この後他の事例も挙げながら、そこにどんな合理性があったのか、なかったのか、順を追ってみていくこととする。
文字文献として古代文化を代表するの
は「古事記」「日本書紀」「万葉集」などである。しかもこれらの文献のなかでは中国から文字が伝来する以前の、あるいはながく文字を使わなかった民衆の文化(無文字文化とか口承文化と呼ばれる。この稿では後者を使う)が色濃く反映されている。その代表的なものが記紀・万葉集のなかで「歌謡」と呼ばれている歌である。この歌謡のなかに「国見の歌」というものがある(国見、歌謡、口承文化などは後で詳しく述べる)。
国見というのは、自分の国や村を、その住民が小高いところから見て誉めあげること。基本的にはその土地に育つ農作物の豊かさを言葉によって願う儀礼として始まっている、、その時の誉め言葉を「国見歌」という、、当時民衆は文字表現をもたず、音だけの口頭表現・口承表現であったが、中国伝采の文字を身につけた貴族がそれを文字表現したのが記紀・万葉集のなかの歌謡である。例を挙げると、万葉仮名が漢字の意味を捨てて音だけで、当字として使っているのが、口承の音表現を前提として、それにあわせて書いたことの一つの証だ。
国見歌でよく知られるものに「大和には群山あれど とりよろふ 天の香具山登り立ち 国見をすれば 国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ うましくにを 蜻蛉島 大和の国は」(『万葉集』日本古典文学大系・岩波書店)がある。欽明天皇の歌となっているのであるが、このような国見の歌は当時の農民など民衆が自分たちのために歌っていたものを記紀・万葉集の編者が天皇が歌ったかのように改竄したというのが最近の研究者の常識なのだ。
歌の意味は、大和の住民が香具山に登って自分の国を誉めていると思えばわかりやすい。煙立⊃は豊かさの象徴。海に喩えてさらに豊かさ、「うまさ」を盛りあげる。ここにある国見歌を呪術的性格をもつものとして「呪歌」とも「言寿」ともいう。そしてこの呪術的性格のなかに強力な法則がひそんでおり、なお日本文化の中にひろくゆきわたっているのであるが、それはだんだんと述べていくことにする。
この国見歌の古代的性格がわかると、花見の古代的意味がわかりやすい。土橋寛は『歌謡1』(鑑賞日本古典文学・第四巻・角川書店)で次のように述べる。「国見ということばに対して、花見、山見、雲見ということばもある。国見というのは、春の初め高い所に登って広い国土を見渡すことであるのに対し、他の三語は見る対象を花、山、雲に特定したことばであるが、それらの対象は、いずれも強い生命力を内蔵すると信じられた景物であって、それを「見る」ことを通じて、その生命力を人間の体内に取り入れ、それによって人間の生命力は再生、強化されるという観念と習俗を表すことばである」。
これで花見の古代的意味がわかると思う。「強い生命カを内蔵すると信じられた景物」は花だけでなく山や雲などに及んだ。日本の古い信仰、あるいは風俗としていうと、それはさらに常緑樹(枯れることがないと見られた)の松や榊、竹など。あるいは枯れるとはいえ確実に食物を実らせる稲などがその対象とされてきた。花見が農耕儀礼であったとするのは、このような古代的信仰による。また正月の門松(松や竹ど)も同じ古代信仰によって発生している。しかもこれらもまた現代の日本的風俗として盛んなのである。
みてきたように、現代も盛んな花見、あるいは門松の風俗などは、それを日本(和人)の古代社会からの風俗、あるいは古い型の信仰形態としての文化として見出すことが出来るし、それは古代的意味としてだけでなく、大きな変化(意味の変化や形の変化)をもちながら現代に至っていることがわかる。そしてこの古代的意味(主に呪術的信仰形態)と、その変化の中に、日本(和)人が自ら創ってきた文化の法則、あるいはその変化をもたらす思想(すくなくともその母体)がある。
花見や門松の例に見られる古代からの歴史的流れを日本(和人)文化の基層と考えるら、日本人は長い間この基層を軽視したり見失ってきたのである。そこには大な原因がある。一つは漢字の伝来以来、日本(和人)の貴族がそれを政治的権威として使い、文字を持たない文化を文化と認めなかったせいだ。この考えは今も根強い。二⊃目は日本近代の「脱亜入欧」思想にある。
一方、記紀・万葉集において、本来民衆の文化であったものを改竄した部分があるのが象徴するとおり、原始・古代から民衆の労働や生活の場にあった自然や宇宙への信仰(アニミズム)を天皇制として取り込み、国家祭祀・天皇制信仰に結びつけたのである。この論文はそこにある混同を再び分離し、人類の初期的信仰としてのアニミズムを日本(和人)文化の中に見出し、その後の信仰・宗教と区別していくことになる。現代アニミズムは自然と人問の共存の手掛りとして世界的に注目されている。その意味でも、日本列島に芽ばえていた自然観・宇宙観の、その一端を見ることが出来るだろう。
アニミズムの抽出とともに、基層文化といえる働く者の文化・労働儀礼の典型的例を多くとりあげ、さらに
それらがどのように変化したかを具体的にみていく。この変化の中に体系や思想がある。
